病院で勤務されている医療従事者の皆さんは、日頃より「DNR」、「DNAR」、「full code」などという単語を聞いたり、カルテで見かけたりしたことはあるでしょうか。
私の施設では急性期病院の特性上、上記3つともよく見かけます。
この記事を執筆することにした理由は、SNS上で「あの人DNRだから、吸引処置とかしないよ」などという類のものをいくつか見かけたからです。
この記事ではDNRやDNARの意味合いなどコードステータスについて再確認したいと思います。
 Moegi
MoegiSNS上でも、DNR/DNARに関するとんでもない話を見聞きしましたので、今回題材に取り上げさせていただきました。
コードステータス(code status)とは
医療における「コード(Code)」は、特に救命処置や蘇生行為に関する方針を指します。
codeは患者が急変した際にどのような治療を行うかを決める重要な指標です。
急変がリスクの少ない方でも突然起こり得ることですので、患者全員に対してコードステータス(code status)を事前に決めておくことは困難です。
強いて言えば、免許証やマイナンバーカードによる「臓器提供意思」の欄で「心肺蘇生を希望しない」などと記載するくらいでしょうか。
コードステータスは患者や家族と医療チームが話し合い、患者の意思や状態に応じてコードステータスを決定します。
特に終末期や重篤な疾患の患者では、事前に決めておくことが重要と考えます。あとはご高齢患者でしょうか。
コードステータスの種類
主なコードステータスを一覧にします。
- full code(蘇生処置をする, あらゆる救命処置を実施する)
- DNR(Do Not Resuscitate, 蘇生拒否)
- DNAR(Do Not Attempt Resuscitation, 蘇生拒否, 蘇生を試みない)
- AND(Allow Natural Death, 自然死の許容)
- DNI(Do Not Intubate, 気管挿管拒否)



その他にもマニアックなものや、他の疾患の略語と混同しそうなものもあったので、そちらは割愛させていただきました。
full code
full code(フルコード)は、「心停止時にはあらゆる救命処置を実施する」という意味です。
言い方を変えると、心停止には心肺蘇生(CPR:cardiopulmonary resuscitation)を実施をするということです。
もちろん、ECMO、気管挿管、人工呼吸器管理、除細動器の使用、昇圧剤の使用や輸血・輸液負荷による血圧維持、そして血液浄化療法も含めた全ての処置をします。
要は延命治療をするということです。
特に取り決めの無い全ての患者は、基本的にはfull codeとなります。
医療従事者目線で厳しい状況と言わざる得ない状況下でも、ご家族から「全てやってください」と言われたら実施しないといけないのがfull codeというわけです。
当然ながら、蘇生行為中でもご家族より「もう結構です。蘇生行為を終えてください。」と希望があれば終了することになります。



「ご家族が到着するまでは処置を続ける」というパターンは良くありますね。
到着されてから死亡確認・・・といった流れです。
DNR(Do Not Resuscitate)
本記事の本命の一つです。
DNR(Do Not Resuscitate)は、「蘇生拒否」としばしば表現されます。
DNRは、患者が急変して心肺停止に陥ってしまった場合でも、救命処置をしないという意味です。
原則、事前に患者ご本人やご家族さんに事前に確認をして、しっかりと書面でやり取りをして方針を決めます。
「原則」というのは、最初はfull codeであったため蘇生行為を実施していたが、ご家族への再確認で処置を終了してほしいと方針が変更となれば”full code→DNR”へ切り替わり、蘇生行為を終了する・・・という意味です。
先述しましたがDNRというのは、ご高齢、終末期や重篤な疾患の患者で事前に決めておくというものであると認識しておいてください。
DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)
続いて、本記事のもう一のつ本命です。
DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)もまた「蘇生拒否」表現されます。
それだとDNRと同じですので、当然意味合いが異なります。
DNARの”A:Attempt”の意味は”試みる”という意味ですので、「蘇生を試みるな」というのが正確なところです。
要は、DNRだと「蘇生できる可能性のある場合でも蘇生をするな」という意味にも捉えられてしまうです。
「救命する見込みが無い患者に対して蘇生を試みるな」という意味合いのDNARを使用するのが良いという論文が1989年に公表されてから全世界でDNRではなくDNARが使用されることとなったのです。
ですので、厳密にはDNRとDNARは意味は異なるのですが、臨床現場では同じ意味合いで使用されます。



DNR/DNARオーダーというのは、終末期に望まれない・不要な侵襲的治療を回避するための指示・方針というわけです。
AND(Allow Natural Death)
いつから提唱されてきた?
AND(Allow Natural Death)は、「自然死の許容」や「自然死の受け入れ」などと表現されます。
ANDは1990年代後半から2000年代初頭にかけて、アメリカのホスピス・緩和ケア分野で提唱され始めた概念です。
2005年以降にアメリカの一部の病院や医療機関がDNRの代替としてANDを採用されており、特に小児医療や高齢者医療において、家族への説明の際にANDが用いられるケースが増えていたようです。
そして2008年頃から、アメリカの医療倫理団体や緩和ケア関連の学会でANDの使用が推奨されるようになり、2010年代には欧米の一部の病院でANDがDNRと同等の選択肢として記載されるようになりました。
近年では、日本を含むアジア諸国の緩和ケア領域でもANDの概念が認識されつつあるようです。
DNARに代わる表現へ
DNARが普及していますが、「蘇生を試みるな」という否定的な意味合いをDNARは持つので、受け入れ難い表現ではあります。
ANDだと「最期は自然な形で迎えたい」という表現であるので柔らかい表現であることもあり、より患者に権利が尊重されるような表現であるためにDNARに変わる表現としてANDが普及しつつあるようです。
ANDの分類
少し余談的な内容ですが、ANDはintermediate ANDとcomfort support ANDに分類されます。
心停止時にCPR(心肺蘇生)を実施しないが、心停止に至るまでの期間は全ての医療処置、看護処置を実施を受けるというもの。つまりは、DNARと同意。
緩和医療へ実施し、心停止時におけるCPRだけでなく、全ての治療や医療処置を差し控えるというもの。つまりは終末期医療の概念であり、BSC(best supportive care)やCMO(緩和優先医療:comfort measures only)が該当すると考える。



ただ当院でもまだまだカルテには「DNAR」と記載されており、一度もANDという記載を見たことはありません。
DNI(Do Not Intubate)
DNI(Do Not Intubate)は「挿管はしない」という意味のコードステータスとなります。
ポイントはDNIのみの取得だと、挿管はしないが、心停止時のCPRや昇圧剤の投与などの救命処置はされることになります。
・・・なんか、侵襲的に救命処置をしたいのかしたく無いのかが分かりにくいですね。
DNIはpartial DNRの一種と言えそうで、partial DNRは患者の自律性を尊重している結果のステータスコードとも取れますが、本来のDNR/DNARの概念や解釈を誤解させてしまうような表現のため、使用すべきでないとされています。
私個人的にですがDNIは、「呼吸不全が重症化しており今後も改善の見込みが極めて低い場合に、人工呼吸器での呼吸管理が必要となっても挿管はしない」という意味合いで使用する感じかと思っています。
・・・といっても、わざわざDNIを取得せずに、ANDもしくはDNARを取得すれば良いのだとは思いますが、「挿管をしない」ということを強調したいのでしょうね。
ですので、partial DNRというのは好ましくないと言われているのでしょうか。
この記事の意図とは・・・?
単にコードステータスを理解してもらうだけなら本記事は執筆していないことでしょう。
もちろん、DNRとDNARの意味合いの違いやANDなどの新しい概念の紹介という目的はあるのですが、このDNR/DNARを誤解している方がいらっしゃるようで、SNS上でも「DNARに関してとんでもない勘違いをしている人がいる!!」という投稿を見かけたのでこの記事を執筆することにしたのです。
医療従事者がDNARを誤って解釈しないようにしなければいけませんし、解釈の誤用によって、患者及び患者家族に医療従事者による不利益を受けないようにしなければなりません。
実はこのDNARの解釈についての見解が日本集中治療医学会倫理委員会より報告が出されています。
医療従事者の方へは、是非一読していただきたいものです。
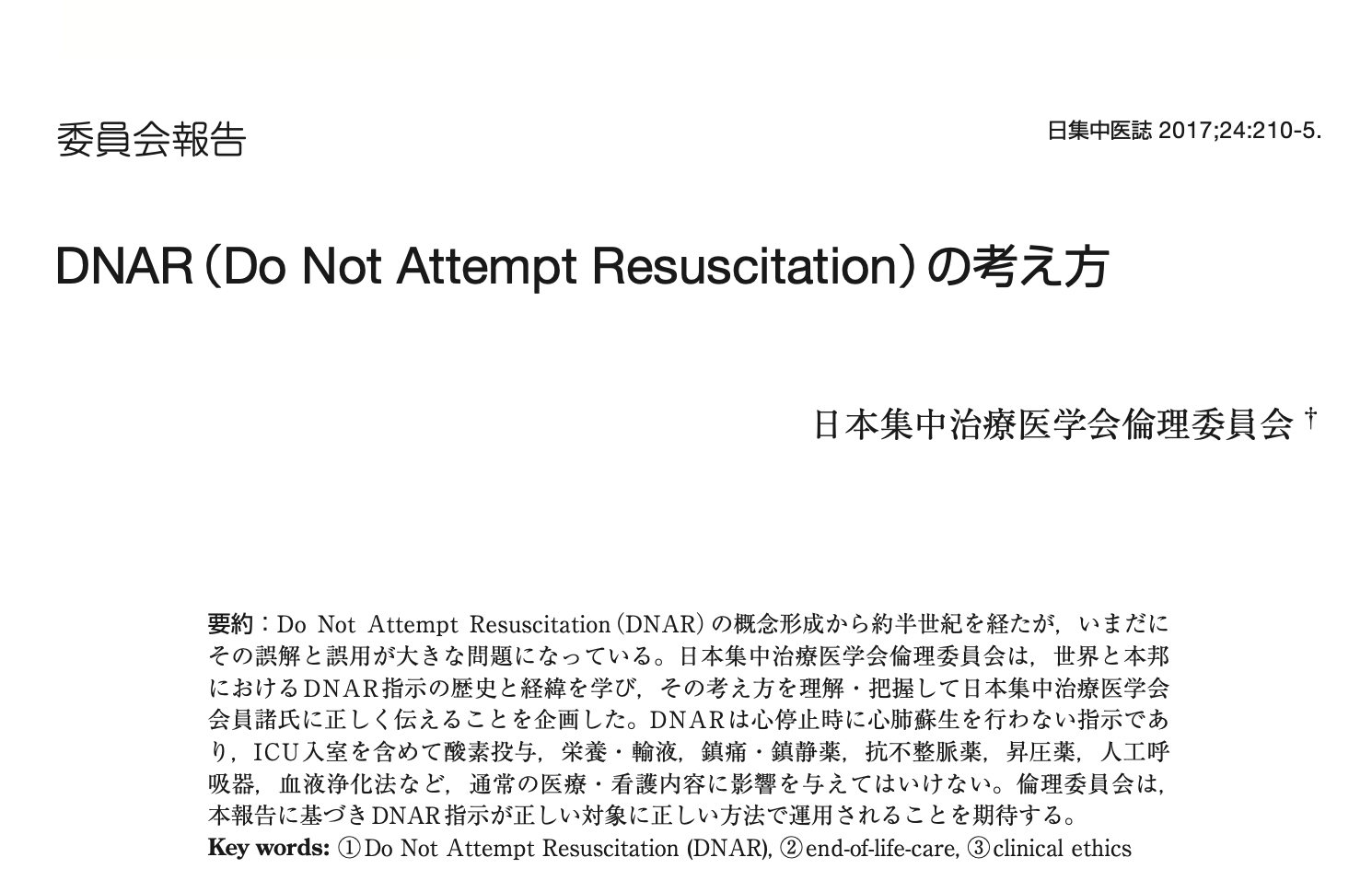 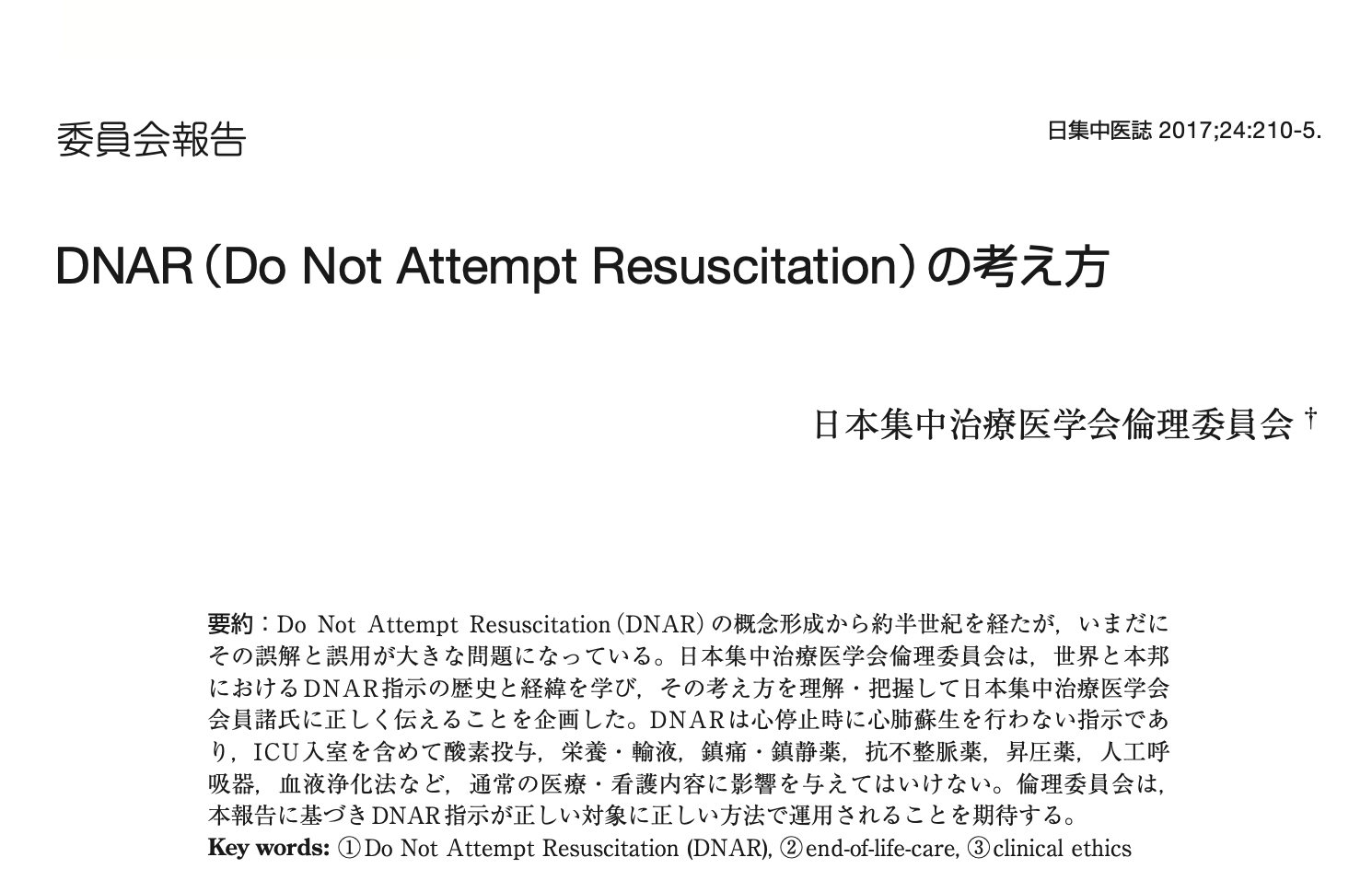 |
『DNAR (Do Not Attempt Resuscitation)の考え方』
日本集中治療医学会倫理委員会, 日集中医誌 2017;24:210-5.



日本集中治療医学会倫理委員会の報告は上記リンクより確認ができます。
「DNR/DNARだから処置はしない?」・・・ではない!!
これまでに登場したDNR, DNAR, ANDは多少の違いはあれど、ほぼ同意の意味であることは確認しました。
このDNR, DNAR, ANDは、心停止に対するCPRに対してのみ適用されることに留意します。
心停止となった患者にDNARやANDオーダーが出されていない限りはfull codeですので、医師指示を待たずにCPRを開始する必要があります。要は胸骨圧迫です。
CPRを開始しなくても良い、もしくはCPRを中止するのは医師よりDNARやANDの指示が必要となるのです。
そして、この記事で最も言いたいことは
DNARやANDオーダーというのは、心停止によるCPR以外の治療や看護ケアに影響されることは無い
ということです。
DNARやANDが取得されている患者は、あくまでも心停止時にCPRや昇圧剤の使用、挿管などをしないということであり、酸素投与、点滴、吸引などの処置は提供し続ける必要があります。
もちろん、栄養の投与や苦痛緩和の薬剤投与はしますし、体位変換やオムツ交換など看護ケアをし続けます。
いや、むしろ、終末期医療・緩和ケアのフェーズであるなら尚更、しっかりとケアをして、満足度の高い良い日々を過ごしていただけるように努めるべきなのです。
大事なことですのでもう一度言います。
DNARは心停止にのみ適応される指示であり、
その他の治療や看護ケアをしなくても良いというものではありません。
日本集中治療医学会倫理委員会の報告に、”最後に,DNAR指示は心停止時に心肺蘇生をしない指示であり,通常の医療・看護・ケアに影響を与えないことを再確認したい。”と綴られています。
今一度、DNARやANDに関して、再確認をしていただければ幸いです。
さいごに
SNSのどこかで、「あの患者DNARだから、酸素投与も吸引もしないよ」とか、「DNARだからオムツ交換は頻繁にしなくても良い」などというとんでもない発言を見かけた気がしたので、今回DNARやANDの概念という内容で説明させていただきました。
私達CEは終末期医療や緩和ケアになかなか介入しないので、今回せっかくコードステータスの話をさせていただいたので、BSC(best supportive care)やCMO(緩和優先医療:comfort measures only)、ACP(advance care planning)などが少々ややこしいので、次回触れてみたいと考えています。



















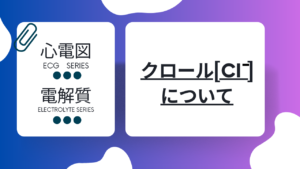
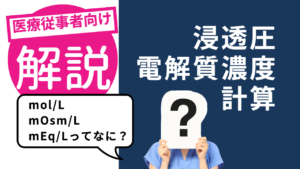
コメント