ご存知の通り、私MoegiはCEとして内視鏡業務を担当しており、先生方と日本一の内視鏡チームを目指して日々治療の介助をしています。
X(旧:Twitter)界隈でも、内視鏡業務に就かれている熱心なCEさん、そして消化管内視鏡医の先生が何人もいらっしゃいます。
内視鏡業務というのは、CE界隈では介入していない施設も多く、CE業務としてもまだまだこれから拡大していく業務だと認識しています。
さて、本記事をご覧になられているということは、「内視鏡業務に業務があるが、業務する上でのポイントは何か?」、「内視鏡業務がなかなか上手くできないから、何かコツは無いの?」ということを知りたい読者さんとお見受けします。
本記事では、内視鏡業務をこなしていく上で私が意識していることをお伝えします。
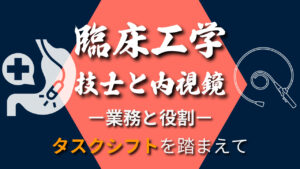
はじめに
本記事では、内視鏡業務全般についてのポイント解説となります。
やはり、皆さんが知りたいことと言えば、「ESDの介助のコツは?」、「EMRとCSPのスネアリングのコツは?」といったところが一番気になっていらっしゃる部分かと思います。
ですが、今回はESDやEMR、ERCPといった個々の詳しいポイント解説はしないのでご了承ください。
あくまでも、“内視鏡業務”に対する意識付けのポイントになります。
 Moegi
MoegiESDやEMRなどの個別解説は、こちらを参照ください。


内視鏡業務は準備が要!!
内視鏡業務に関わらずですが、
準備が肝心
となる業務です。
内視鏡業務を担当することとなった新人へは、何度も言い聞かせるのですが、
ESDは皆やりたいのでESDを独り立ちした身からすると、ESDやEMRに入りたがるのはわかりますが、デバイスの特性、手技の流れなどを理解していないのに介助だけ入るなんて図々しいのです。
求められるデバイス操作ができないことは仕方がないのでサポートはしますが、「デバイス操作が分からない」、「手技の流れが分からない」というのは準備不足以外の何物でもないのです。
私個人の内視鏡業務に対する準備と実際のデバイス操作のウエイトというのは
準備が7割、8割を占める
と考えており、デバイス操作は経験を積むしかないのです。
ESDのデバイス介助には入ったものの、準備不足のせいで必要物品を近くに準備忘れていたり、手技の次の流れを理解していなかったりしたせいで、デバイス準備のために手技を一時中断することに・・・なんてことを起こして先生に迷惑をかけてしまっては、何のためにCEがデバイス介助やデバイス管理を任せられているのか理解できません。
ESDやEMRの手技がこなせることになるためには、様々な準備ができてこそです。



日々、新人へは「準備を疎かにしないこと」と口煩く伝えています。
内視鏡業務における”準備”とは?
「準備が重要」とは言いましたが、もちろん、治療や検査前のデバイスやスコープの準備だけが”準備”ではありません。
知識の習得などもまた準備に含まれます。
“準備”内容をザックリと挙げてみます。
- 消化管の基本的な解剖生理
- 業務マニュアルの熟読
- スコープの種類と特性
- 管理しているデバイスの種類と特性、コストの把握
- 検査/治療する患者や病変の情報
- 病変の分類や診断基準
- 治療する内視鏡室のセッティング
- 電気メスの操作と各モードの特性
- 検査/治療の流れの把握
- スコープ洗浄
- 先生ごとのルールや得意なストラテジーの把握
- 急変時対処方法
・・・まだまだ細かいことはありそうですが、準備すべき内容は大体こんなもんでしょうか。
ESDやEMRの介助に入るよりも大変だということが分かっていただけたかと思います。
もちろん、ESDやERCPの介助は、それはそれで別の大変さがあると思いますが、ベースに上記の準備があってこそのデバイス介助となります。



準備を疎かにすると困るのは自分だけではないということを意識しましょう。
厄介なのは、先生ごとに存在するルール
内視鏡業務に従事されているCEさん、Nsさん達は「あー、分かるわ〜。」と納得していただける事項と思われますが、内視鏡業務で厄介なのは・・・
内視鏡医の先生方は個々にこだわりが非常に強い
ということです。
例えば、大腸内視鏡検査ではスコープの挿入を容易にするために患者さんの体位変換をしますが、体位変換の仕方一つでも脚を組むのか、スコープを跨いで大の字に両脚を伸ばすのか・・・など、先生ごとに微妙に異なります。
他にも、「この先生はこのスコープは嫌いで、あのスコープを使いたがる」、「あの先生のESDでは、これを絶対使用するから確保しておくように。在庫なければ発注かけといて。」・・・などと様々です。
また、ESDのストラテジーに関しても流派が存在することもあるので、「この先生のESDは、基本的にこういうパターンが多いから次は◯◯をするのかな?」などと先生ごとの得意な手技があるので、把握しておくと手技の進行がスムーズになったり、事前に使用するデバイスを準備できたりと慌てなくて済みます。



流派があるとはいえ、それでも先生ごとの細かいルールやこだわりは統一してほしいものです・・・。
各準備事項の詳細
言いたいことは言えたのでここで終えても良かったのですが、せっかくですから先に挙げた準備事項について各項目についてザッと説明していきます。
全部を一気に実行していくのは大変ですが、コツコツと同時並行で進めていきましょう。
消化管の基本的な解剖生理
先生とのディスカッションで、部位の場所などが分かっていないと会話についていけません。
消化管の基本的な解剖整理を覚えましょう。
その際は英語とともに覚えると良いでしょう。


スコープの種類と特性
鉗子口径やアングルがどれくらいまでかかるか等の把握は優先されるべき項目です。
どのデバイスが使用でき、どのスコープの鉗子口は通らないのかを把握しなければなりません。
他には副送水が可能かどうか、拡大スコープかどうかだと思います。
止血等の処置がある場合は副送水、ESD術前検査などの診断では拡大機能が必要です。
その日の内視鏡検査項目と検査数、どの内視鏡検査/治療に対してどのスコープを使用するかの把握をすること、そしてどのスコープが何本あり、洗浄中のスコープ数、あと何分で洗浄が終わるかをマネジメントすることは、内視鏡室が円滑に進行するためのCEの重要な役割と言えます。
自施設で使用しているスコープは最低限覚えましょう。


管理しているデバイスの種類と特性、コストの把握
自施設で管理しているデバイスはどのようなものがあるのか、そして各デバイスの特徴はどのようなものがあるのかの把握をしましょう。
意外と見過ごされますが、1本あたりのデバイスのコストにも気にかけることが重要です。
デバイスというのは病院持ち出しとなるので(患者に請求できるものもある)、できるだけコストは削減したいのです。
クリップ1本でもコストダウンを考えている施設もあります。
ESD1回の診療報酬がいくらかを知った上で、使用するデバイスのコストを意識すると良いでしょう。
ESDの診療報酬点数を挙げておきます。
EMRはESDの3分の1程度となります。
- 食道ESD ・・・ 22,100点
- 胃ESD ・・・ 18,370点
- 十二指腸ESD ・・・ 21,370点
- 大腸ESD ・・・ 22,040点



私の施設の場合、大学病院ですから、結構デバイスをポンポン出しますので、コスト意識は低いと思います。
完全にコスト意識がゼロというわけではありませんけども。
検査/治療する患者や病変の情報
治療の介助に入るにあたり、どこの部位の病変でどんな病変なのかの情報収集は重要です。
事前情報を知っているかどうかで、気の持ちようが異なります。
同じ胃でも、見下ろしか見上げでも変わりますし、繊維化してそうかな・・・などという感じでしょうか。
敵を知り己を知れば百戦危うからず
「よっしゃESDの介助入るぜーっ!!」と思っていたら、十二指腸ESDだったからメチャクチャしんどかった・・・などということもあります。いや、そんなことは無いとは思いますが・・・。
病変の分類や診断基準
病変の分類、診断基準については、もちろん診断は医師のみができることですが、「この病変はCSP。こっちの病変はEMR」、「この病変は深そうだな・・・。」という判断が自分の中でできるようになるのも良いですが、先生とのコミュニケーション/ディスカッションの幅が広がります。
ここが理解できる/できないで、内視鏡治療の面白さが断然違ってきます。
内視鏡室のセッティング
デバイスカートや電気メスの配置、ガーゼやゼリーなど細々した物品の準備は、”準備”の基本と言っても良いでしょう。
先生が気持ちよく手技ができるように、電気メスやジェットの位置などはこだわりを持っても良いと思います。
自分はデバイス介助に入るから、セッティングはNsにやってもらえば良い・・・ということにはならないようにしましょう。
電気メスの操作と各モードの特性
電気メス一つにしても奥が深いのです。
デバイス交換時の設定変更のスムーズさ、出血した時のsoftCOAGへの素早い変更など操作を覚えること、剥離層の血管分部によって、凝固モードをSwiftにするのかForcedにするのかモードの特性の把握も重要です。
検査/治療の流れの把握
胃カメラ、大腸カメラ一つでも検査の順序や流れというのがあり、体位変換や患者の背中をさするなどポイントがあります。
ESDについても、例えば、拡大→局注→切開→フラップ作成→全周切開→トラクション→トンネル掘り・・・という大まかな流れがあるので、基本的なストラテジーを頭の中に叩き込んでおきましょう。
スコープ洗浄
さて、いくらデバイス介助ができても、後片付けができなければ、ESDの介助なんて入らなくて良い・・・と思われても仕方ありません。
スコープ洗浄も早めに習得してしまいましょう。
先生ごとのルールや得意なストラテジーの把握
「厄介なのは、先生ごとに存在するルール」の項で述べた通りです。
いかに術者の先生がスムーズに、気持ちよく手技ができるように介助するのかが重要です。
急変時対処方法
内視鏡室でも当然ですが、急変が生じ得ます。
- 過鎮静によるSpO2低下
- 窒息
- 出血性ショック
- CPA
ちなみにですが、私は内視鏡室でのCPAを経験したことがあります。
毎年、急変時シミュレーションを実施して対策をしています。
BLSや人工呼吸器、除細動器の操作方法などの確認をしておきます。
さいごに
以上で、内視鏡業務における意識しておくべきポイント解説を終わります。
今回は業務全体における心得ということで説明をしましたが、ESD介助のポイントやCSP/EMRの介助のポイントなども今後展開できたらと考えています。
これからの内視鏡業務を盛り上げていきましょう。

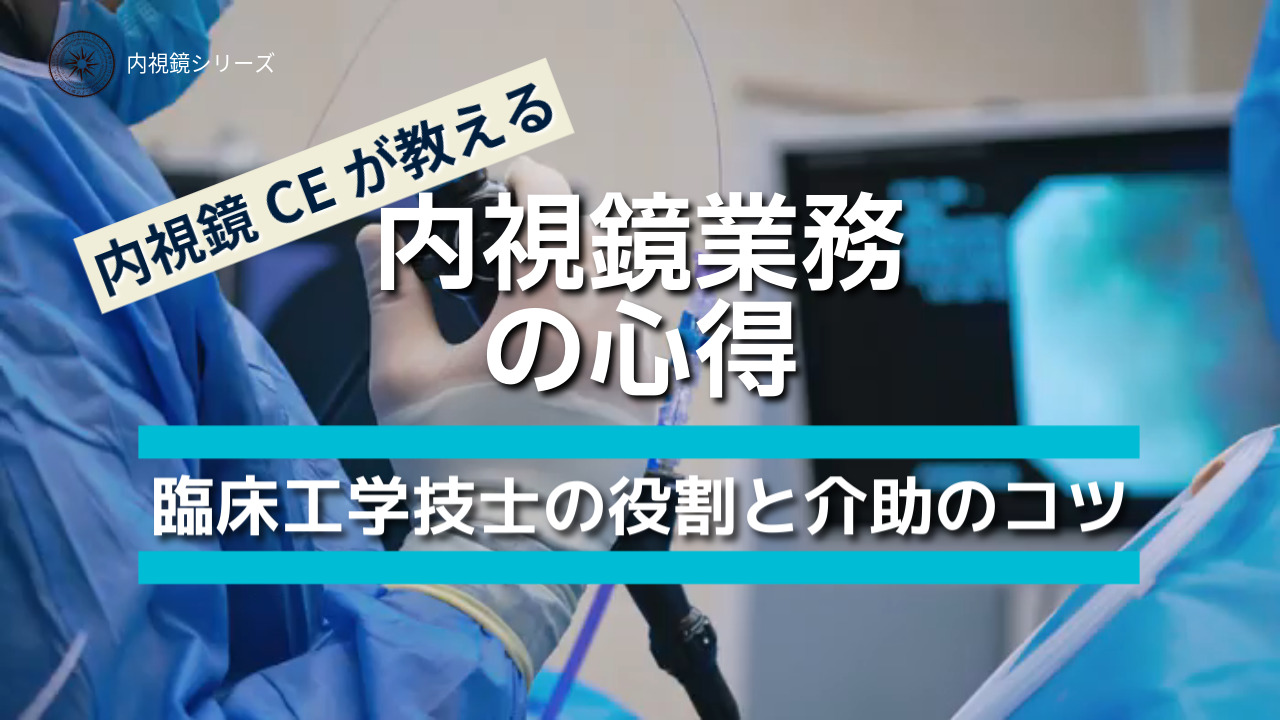











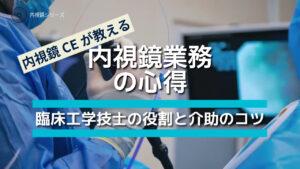
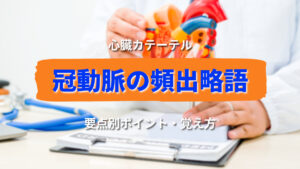







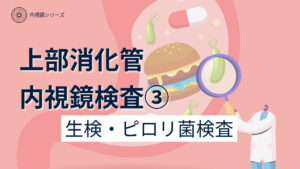



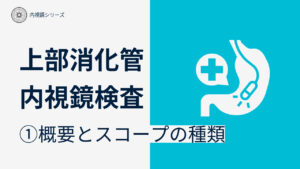
コメント